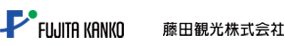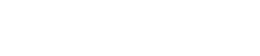旅のご提案 ~時代を捉えた温かいサービス、かけがえのない一日のご提供

2020年01月14日
江戸の三大名鐘を巡る
江戸の代表的な寺院の鐘が、様々な文献で紹介されています。
諸説あり、文献によっても組み合わせが異なりますが、かつて「江戸三大名鐘」と呼ばれていた鐘があり、中でも「今鳴るは 芝か上野か 浅草か」と、江戸時代に詠まれた川柳の中にある「芝三縁山増上寺」、「上野東叡山寛永寺」、「浅草金龍山浅草寺弁天山」の三つの鐘が庶民の間で親しまれていたそうです。今回は、歴史好きの方にオススメ、今も残る「江戸三大名鐘(増上寺・寛永寺・浅草寺)」を紹介いたします。

徳川将軍家の菩提寺として有名な東京都港区にある「増上寺」内にある、鐘楼堂に掛けられている大梵鐘は、4代将軍 徳川家綱の命により1673年に鋳造されました。
江戸で鋳造されたものの中で最も古く、江戸で初めての梵鐘として知られています。高さ約3.3m、直径約1.8m、重さ約15t、関東最大級の鐘で、あまりの大きさに7回の鋳造を経て完成したとも言われています。鐘楼のデザインは非常に美しく丁寧に鋳造されています。

東京都台東区にある「寛永寺」に設けられた上野の鐘楼は、今現存する鐘が二代目で、1787年に鋳造されたものです。高さ約1.7m、直径約1.1mの大きさで、台東区の有形文化財に指定されています。
設置されている場所は、上野の山の中で高い位置にあり、松尾芭蕉の「花の雲 鐘は上野か 浅草か」という句のモデルになったとも言われています。度重なる罹災により顔だけになった「上野大仏」のすぐ近くに位置し、今も正午と朝夕6時の計三回、毎日時を告げ続けています。

東京台東区にある「浅草寺」本堂南東にある小高い丘は、弁財天を祀る弁天堂が建つことから弁天山と呼ばれています。この弁財天は神奈川県藤沢市の江ノ島弁天、千葉県柏市の布施弁天と並んで「関東の三弁天」として名高い弁財天です。弁天堂に向かって右手に鐘楼があり、そこに掛けられている鐘を「時の鐘」と呼び、江戸の市中に時を告げていた鐘の一つに数えられていました。
高さ約2.1m、直径約1.1mの大きさで、戦時中、多くの寺の鐘が供出を余儀なくされた中で、特に由緒がある鐘ということで残されました。現在台東区の有形文化財に指定されており、今も毎朝6時に役僧によって撞かれています。こちらも先述の芭蕉の句のモデルとして知られています。
各々大変人気のある寺院です。大晦日や三が日は大変混雑していますので、ちょっと落ち着いた今の時期に足を運ぶとゆっくり見ることができます。三鐘とも比較的近場で回れますので、歴史がある「江戸三名鐘」をゆっくりと巡ってはいかがでしょうか。
江戸三名鐘巡りに、オススメのホテル
ホテルタビノス浜松町(東京都港区)
住所:東京都港区海岸一丁目13番3号
『Active&Relax』 日本の旅の中心にあるトラベルハブホテル。
羽田空港(東京国際空港)へもアクセス抜群で旅の拠点としても人気のエリア「浜松町」。「東京」「品川」といった主要駅へも電車で約10分とアクセス抜群。お台場や東京タワーといった、観光地にもほど近く、東京観光の拠点として最適な立地です。