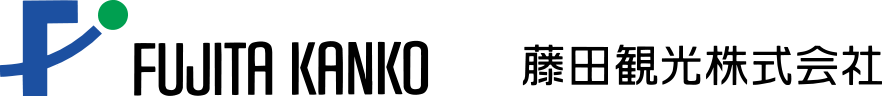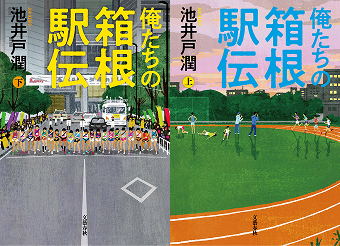Chapter
1
『俺たちの箱根駅伝』と
藤田観光
箱根駅伝が魅力的な理由
本日はホテル椿山荘東京にお越しくださいましてありがとうございます。近著『俺たちの箱根駅伝』を楽しく読ませていただいたところですが、執筆されたきっかけはどのようなものだったのでしょう。
日本テレビが毎年放送する「箱根駅伝」は、まさに青春ドラマの集大成のような素晴らしい番組です。箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)そのものは1920(大正9)年から続く歴史のある大会ですが、全区がテレビ中継されるようになったのは比較的最近の1987(昭和62)年から。それまでの放送技術では、箱根の深い山々に囲まれた道から「生」で放送することは不可能とさえいわれていたんです。だから、それまでどこの局も放送していませんでした。技術の壁が高すぎて、できなかったんですね。しかし、当時のプロデューサー・坂田信久さんとディレクター・田中晃さんを中心とした制作スタッフたちは、「なんとしてでもこのレースを生で届けたい」という情熱のもと、様々な工夫によって不可能を可能にした。テレビマンとして、決死のチャレンジと奇想天外ともいえるイノベーションの塊であるこの放送の秘密に、私自身、心を動かされたのが小説のきっかけです。
不可能を可能にした強い思いと情熱、とても魅力的ですね。
どこの組織でも、上から降ってくる企画というのは少なくないはずですが、「箱根駅伝」を生中継するという挑戦は、まさに現場からボトムアップで生まれたものです。しかも正月の2日間の早朝から昼過ぎまでを費やす大型番組ですから、失敗するわけにいかない。事実、日本テレビ社内では、この企画は出しても出しても、なかなか通らなかったそうです。プロデューサーの坂田さんが素晴らしいのは、それでも腐らず、企画が通らないのは自分に任せてもらうだけの信用がないからだと考え、「全国高校サッカー選手権」の中継を提案して成功させるなど、輝かしい実績を積み上げ、満を持して企画を再提出、承認を得たといわれています。
「箱根駅伝」のエピソードには枚挙に暇がありません。その中でも、私がいちばん面白いと思ったのは、地名でしか呼ばれないはずの中継ポイントの中でなぜ「小涌園前」だけが、施設名で呼ばれるのかということです。
作品のなかで、「もし、あのとき小涌園が大広間を提供してくれなかったら、『箱根駅伝』というコンテンツは存在していなかったかも知れない」、「ホテルの名前を連呼することで感謝の意を表したのである」と書いてあり、読みながらとてもうれしく感じました。
私が「箱根ホテル小涌園」の総支配人に就いたのはもっと後になってのことなのですが、そのエピソードについては先輩たちから聞いています。制作スタッフたちは万全の準備をしていたにもかかわらず、忙しさのあまりスタッフの宿泊場所が確保できていなかった。当時、お正月の箱根は予約でいっぱいですし、そもそも300名が泊まれる宿泊施設もなかったはずです。宿泊できないと箱根での中継は難しいとご相談を受けたということですが、いったんはお断りすることになりました。
相談があったのは、前年の秋、本選間近の頃だったそうですね。
そうです。当時、お正月のホテルはご家族のお客さまで満室状態でした。しかし、団体専用の宴会場である大広間が空いていたんですね。今は大広間に泊まっていただくことはできませんが、寝るだけでいいなら場所は提供できると、日本テレビさんにお伝えしたということでした。
関係者から、もしそのとき大広間を貸してもらえなかったら、「箱根駅伝」の中継はできなかっただろうと聞いています。
テレビの中継も大変ですが、一冊のご本を書きあげるのにも、相当なご苦労がおありだろうと思います。『俺たちの箱根駅伝』はいかがだったのでしょうか。
箱根駅伝は人間味にあふれていて、どのように書いても良いストーリーになる題材ですが、エンタメとして書くとなると、実在の大学名をどう出すのか、あるいは出さないのか、そのあたりの設定が難しかったですね。はじめは実在する大学を舞台にした、架空の選手を主人公に据えようと考えていたんです。ですが、当然のことながらその大学には今箱根駅伝を真剣に目指している選手がいて、それを見守るOBやファンが大勢いらっしゃるわけです。そんな大学を面白おかしく小説の舞台にするのはどうしても気が引けるし、そもそもやるべきじゃない。
競技に真剣に取り組んでいる選手たちへのリスペクトは書く上での絶対条件だと考えていましたし、箱根駅伝の伝統を築いてきた人たちの想いも伝える作品にしたい。じゃあ、架空のチームばかりでいいかというと、それではリアリティがなさ過ぎる。そんなわけで、いざ書こうとして何年も書けませんでした。
そこにようやく目処が立ったのは、何年か前の中継を見ていて、「関東学生連合チーム」だったら書けるんじゃないかと気づいたからです。『俺たちの箱根駅伝』は、関東学生連合チームを主人公たちの舞台としつつ、彼らを通してリアルな箱根駅伝のドラマを表現することで成立しています。
作品では、甲斐監督のキャラクターが印象的でした。要所で的確なアドバイスをする、彼の人を見る観察眼に感心しました。リーダーとしての視点、人を動かす力というのでしょうか。選手たちをきちんとグリップしながら見守るという監督のふるまいが非常に心に残りました。
読者の立場、お客さまの立場になって考える
池井戸さんの作品では、登場人物が様々な困難を乗り越えていく姿が描かれます。ついつい応援しながら読んでしまいますが、書く時にいつも心がけていることはありますか。
「登場人物の言動が自然であること」を意識しています。書き手が用意したストーリーに沿って動くのではなく、その瞬間、その場面で、この人物ならこういうだろう、こうするはずだ、というリアリティを優先して書いているつもりです。いわば登場人物たちが勝手に動くわけですから、物語を綴る作家は大変なのですが、その先の読めないところが読者はおもしろいはずです。
小説の登場人物は、リアルに生きている人と同じだと思います。善悪を安易に決めつけないようにしていますし、書きながら、私自身が「あ、この人はこういう人だったんだ」と発見することもあります。
小説の書き方にルールはありませんが、作者の都合を優先させて書く小説があったら、きっとその物語は不自然にゆがんでしまう気がします。
おっしゃる通り、自分の都合を優先させたものには人は共感してくれないのかもしれません。
私どもの場合を考えますと、お客さまは十人十色。趣味趣向が異なりますので、礼儀正しく接したほうがいいお客さまもいれば、フレンドリーにお声がけしたほうがいい方もいらっしゃいます。こちらの想いだけ、都合だけでするお仕着せのサービスでは、お客さまには伝わらないように思います。お客さまが何を求めているのか、そこを見抜く力が必要ですね。
私にとっても読者はお客さまです。難しいのは、全てのお客さまが等しく満足する小説も、サービスもないということです。同じことをやっても、「これは良い」といわれることもあれば、「全然違う」といわれることもある。全員が納得する正解はありません。
私はいつも小説と真剣勝負だと思って向き合っていますが、ネットの読者レビューを読むと、どう書いても悪い評価をする人が一定数いらっしゃいます。先輩の作家にはそういったレビューは一切見ないという人もいますが、私はどんな風に読まれているのか気になるタイプなので、できるだけ読者の意見には耳を傾けるようにしています。これはとても参考になりますが、藤田観光さんと違うところは、私の場合、読者の皆さんは直接名前も顔もわからない匿名のベールの向こうにあって、直接接しているわけではない、というところでしょうか。
私たちにとって、お客さまの評価は非常に重要ですし、常に肌身で感じ意識しています。しかし、例えばサービスや食事はよいがコストパフォーマンスの評価だけ低いということもあります。とはいえ5万円の客室を2万円にすることはできないですし、するべきではない。お客さまのご要望に対して、何をどこまで追求するのか。できるのか。そこはとても悩むところですね。
どんなお客さまに合わせていくのか、サービスのどこに重点を置いていくのか、はまさに経営判断そのものですね。